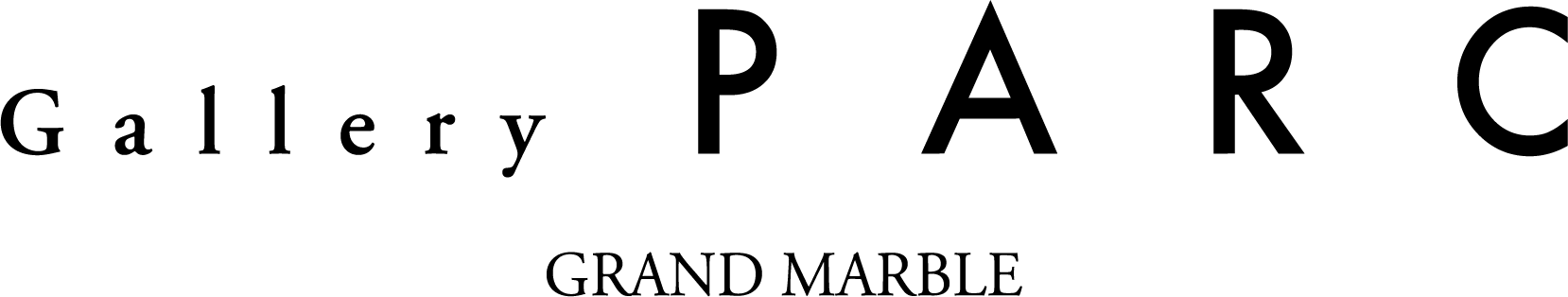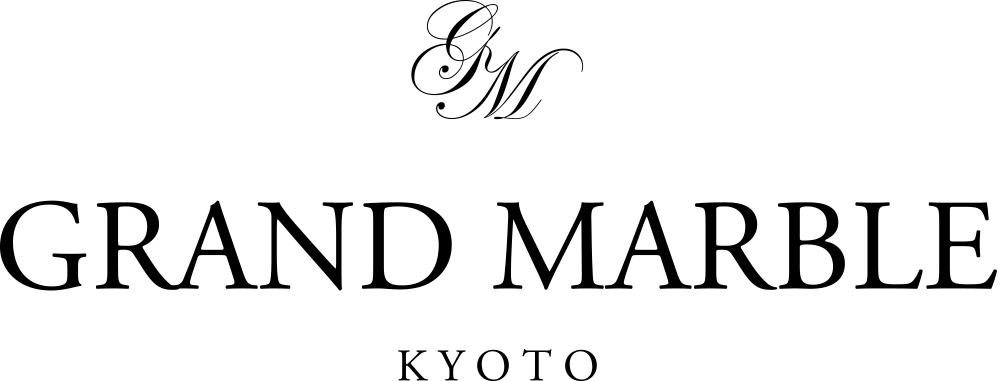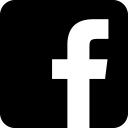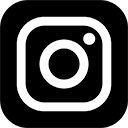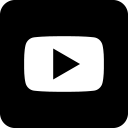2018.5.4. ~ 5.20.
Statement
六甲山の麓には山からイノシシが下りてくる。2016年に神戸の団地を撮る機会があり、下見を兼ねて六甲周辺を散策していると、至る所にイノシシが描かれた看板を見つけた。僕はその絵を見て数少ない神戸での記憶を思い出す。僕は、幼い頃に神戸市内で過ごした時期がある。今では当時の記憶はほとんど無く、数少ない記憶の一つにイノシシに遭遇した事がある。その情報を思い出しただけではあるが、看板を通して今も変わらずに神戸にイノシシが出ること知った。僕にとって神戸の街並みは、山の中にすっぽりはめ込まれた街である。住宅街と言っても街の端まで行けば落石防止のネットで行き止まりとなったり、橋のない渓谷で道を迂回するなど、決して都市とも田舎とも言えない場所である。それこそ、その場所は自然と人為が折り重なった場所と言えるのではないだろうか。
六甲山は、古くから森林などの伐採や燃料材の確保などを繰り返して行くうちに山は荒廃していいった過去がある。荒廃の結果、土砂災害が頻発させることとなり、明治以降に土砂災害対策で植林を施すことや治山事業が活発化していく。そして、1960年以降には山中に都市を作る開発が始まり現在の街並みへと繋がる。この一連の流れは、人の暮らしに必要とされた形で何度も調整された自然の形なのだろう。人為的自然ともいうべきなのだろうか、そして、人間が主体ではない自然とは何だろうか。それは、網目越しの彼方から突然現れるイノシシだ。彼らは、不意にやってくる。それでも閑静な住宅街は、依然として閑静なままだ。
ならば、人もイノシシもいない写真を見た時、僕はどんな思いをするのだろう。この場所で写るものは何があるのか。SNSで画像付きの投稿を見て、獣害を受けた地域を巡りながら写真を撮っていく事をした。撮った写真を見返して行くうちに、極端に視線が低い写真があることに気づいた。その低さは、生き物を彷彿とさせ自身で撮った身体ではないような違和感を感じさせる。斜面を歩く時、人は顔を正面に向けることはそう容易いなことではないと思う。傾斜が厳しいほどに空を仰いでしまうか、或いは地面を見てしまうかではないだろうか。でないと、先も足元も見ることが出来ずに躓いてしまうからだ。では、顔を水平垂直にした時どのように見えるのか。それは、写真で起きたように視線が低くなる。この瞬間、僕は地形によって影響を受けた視線があることを経験した。紛れもなくシャッターを押したのは自分ではあるが、地形にも手というものがあるとすれば、僕に手を沿わせた結果として視線の低く感じさせるのかもしれない。と同時に「僕が見た」という指標は「地形によって僕は見せられた」という指標へと変換が起きる。
ヴァルター・ヴェンヤミンの『写真小史』でこのような一節がある。「カメラに語りかける自然は眼に語りかける自然とは違う。その違いは、とりわけ、人間の意識に浸透された空間の代わりに、無意識に浸透された空間が現出するところにある」。ヴェンヤミンに倣って言えば、地形が映像に影響を及ぼした結果、写真(自然と人為の視線が交錯する)として見る事が出来るのではないだろうか。
最近、知人との会話で、京都の平安神宮に現れたイノシシは二条城まで走り、外堀に飛び込み命果てたという話を聞いた。
About
2010年に日本大学芸術学部写真学科古典技法コース卒業、2012年に京都造形芸術大学大学院修士課程芸術表現研究科芸術表現コースを修了した守屋友樹(もりや・ゆうき/1987年・北海道生まれ)は2017年「still untitled & a women S」(KYOTO ART HOSTEL kumagusuku・京都)、2015年「消えた山、現れた石_ gone the mountain/turn up the stone」(Gallery PARC・京都)などの個展に加え、多くのグループ展などによる写真・インスタレーション作品の発表。また京都を拠点に活動する演出家・和田ながら(したため)とのパフォーマンスユニット「守屋友樹と和田ながら」公演として、2016年の『石|溶けちゃってテレポート、固まってディレイ』(アトリエ劇研・京都)をはじめ、2017年の亀山トリエンナーレで『山と海に貼り付けた』(三重)、2018年のSICF19での『石|溶けちゃってテレポート、固まってディレイ』(青山スパイラル・東京)に参加するなど、写真表現を中心に積極的に活動の幅を広げています。
2017年の個展「Still Untitled / A Woman S」では、予測や研究がなされながらも、未だ噴火には至らない活火山でのフィールドワークの記録とともに、SNS上で見つけた知人のつぶやきを約一年に渡って追いかけた記録と、実際の本人とのやりとりを重ね合わせて展開。また、「未来の途中の星座‐美術・工芸・デザインの新鋭9人展」(京都工芸繊維大学・京都)では、幼い頃に神戸で遭遇したイノシシの記憶を頼りに現地を取材し、現在でもイノシシが山から下りてくる場所を撮影した写真・映像で構成されました。これらは、近年の守屋のテーマである『写真における「サスペンス(未然の状態、無題の状態)』への考察を主眼に展開させられたもので、本展「シシが山から下りてくる:It come down from the mountain」は、この神戸・六甲山の麓に出没するイノシシを追ったプロジェクトをベースに、開発されて拓かれた土地を人為的自然として、「人間が主体ではない自然とは何か。それは、網目越しの彼方から突然現れるイノシシではないだろうか。」という仮説を起点に、イノシシの存在(不在)を通して「都市/自然/身体」の横断を試みるものです。
山と住宅地の境目にある場所を取材した一枚の写真。これは「かつてイノシシが下りてきた場所」であり、「いま(撮影した時には)イノシシがいない(写っていない)場所」であり、また「いつかまたイノシシが下りてくるかもしれない場所」の写真と呼ぶことができます。しかし、この写真はそのものとしてそれらをなに一つ決定しない、未知・未然が維持された状態にあるとも言えます。私たちは常に未知を既知で、未然を已然でもって触れ、切り取ります。この一枚の写真は、時間・場所・歴史・経験・知識・記録・言葉など、「写真(に写るもの)の外」にいる鑑賞者との交わりによって生じる呼び名(視線)によって捉えられていると言えます。そうしていつしか無題の歌は題詠されたものとして読まれ、そこに受け取り可能な意味を固定化してしまいます。
本展において守屋は写真を過去の既知・已然に固定化したものではなく、過去と現在と未来において未だ意味の固定されることのないひとつの塊りの状態でもあることを示そうとしていると言えます。そうして写真を「サスペンス」との緊張関係に置き直すことで、写真を見る・読む行為において、私たちの内に「わからないもの」を「わかるもの」にしようとするベクトルが常に働いていることを自覚させ、展示はその気づきを促す装置として起動し、鑑賞者に働きかけるのではないでしょうか。